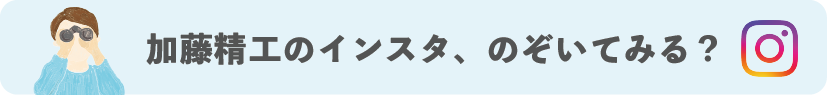消費者課題
納期に合わせる為の計画立て
納期に合わせる為の計画立て
●社内の情報共有
納期が遅延するような場合に連絡を怠れば、お客様の営業活動に影響が生じてしまいます。そのため、本社と各拠点で情報共有をし、適正な需要予測・毎月の在庫の棚卸・適正在庫の推進・発注漏れ防止のため複数人での確認などをおこない、適正な業務執行を徹底し、全ての仕事において納期を遵守します。
●お客様との連携
お客様の長期的生産計画の情報をいち早くキャッチする努力をし、設備投資判断、社内生産工程の工夫、生産工程の変更届けを適切におこないます。そのため、お客様とのコミュニケーションを適切に取り、将来動向の見極めをおこないます。
品質管理の徹底

ISO9001に基づいた品質向上

当社では係長以上の役職者が内部監査員として、定期的に他部署の監査の持ち回りをおこなっています。
ISO09001とは関係なく、特殊な生産工程がある場合、不具合や改善対策の確認が必要な場合などにはお客様の要望にあわせて立ち合いチェックや検査を実施することもあります。
また新製品を生産する場合は計画書を作成し、お客様とその計画に沿って号試・作業標準類作成・行程監査のタイミングなどの全体のスケジュールを確認します。
お客様視点の品質保証
製品の打ち合わせの際には、お客様に部品の使い方等の確認をおこない、それに適した作業工程などを提案させていただいています。
新製品の生産を受注した際は現場の作業者にも、その部品がどのようにつかわれるのかを伝えることにより、部品単体だけを見て作業するのではなく、よりお客様に添ったモノづくりになるように心がけています。
またお客様の製品それぞれに検査規格を設け、管理方法や検査の頻度や方法などを個別に設定しています。
不良品撲滅の目標設定

不良品撲滅の目標設定

「不良品の流出ゼロ継続」目標を大前提に、毎年会社全体での方針と目標設定をおこなっています。そこから各部署や拠点で目標を達成するための施策を検討し、それに紐づく活動を展開しています。特別に状況の悪い部品があれば、部門や工場の垣根を超えて個別のプロジェクトを発足させ、納期目標・不良率・生産量を改善させるべく対応することもあります。また、不良品低減・不良品を見逃さないために、検査環境も整えて管理をしています。
日々の5S活動を徹底し、検査の工程では、自動検査設備に変更する、肉眼の検査から拡大鏡を使用しての検査に変更する、照明をLEDに変えて良好な環境を確保するなどの改善をおこなっています。
設計段階から提案する無駄のない開発サポート

設計段階から提案する無駄のない開発サポート

冷間圧造や旋盤切削といった部品加工を知り尽くした専門家集団がまずは設計図面を深く理解し、お客様が必要としている仕様・機能を実現する最適な加工方法をご提案し、省力化・省資源化による無駄のないもの作りでコスト削減を実現します。
業務改善の取り組み

「いいね賞」
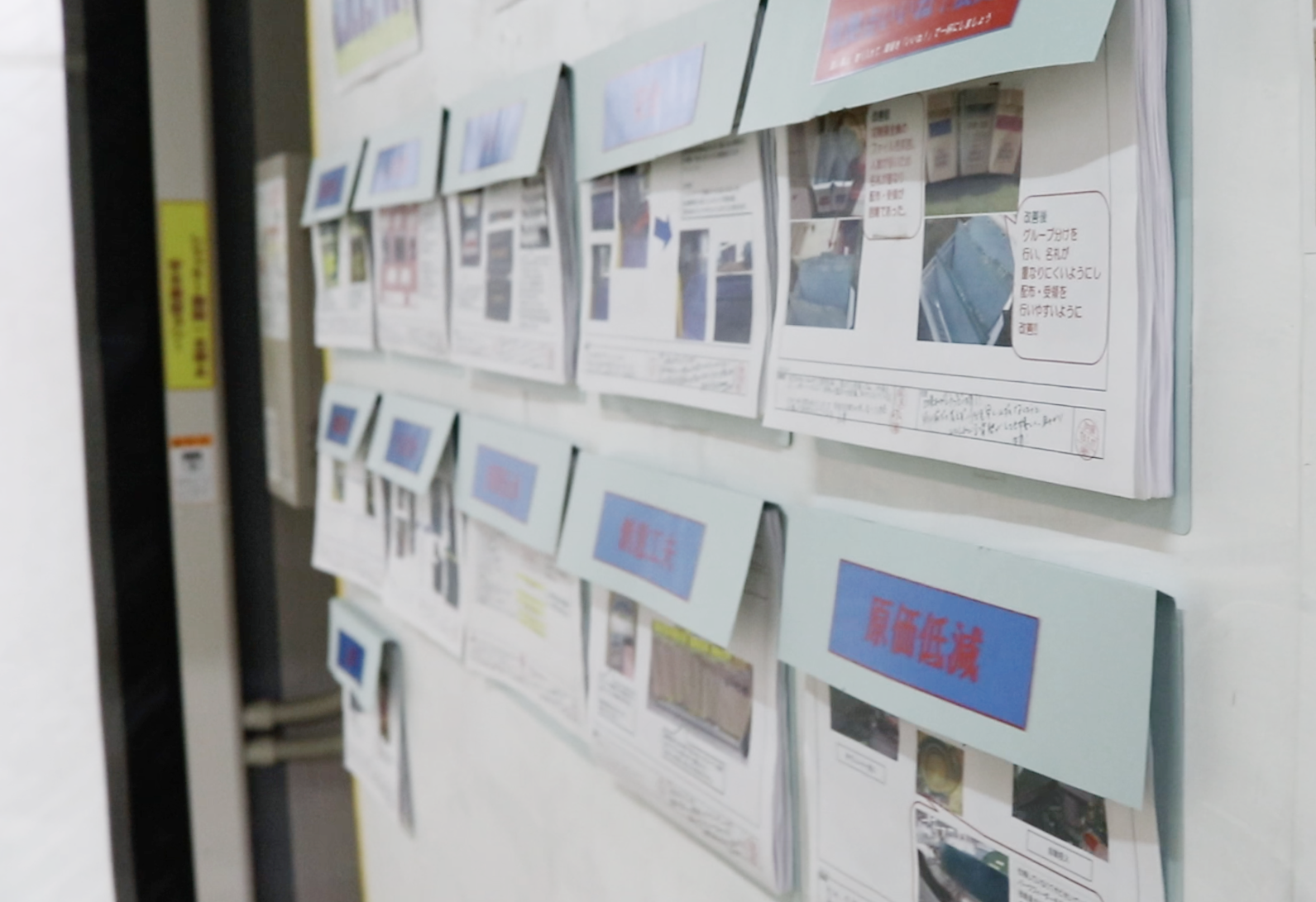
「いいね賞」は各拠点で実施した改善を報告し、上司や社長がその改善に対して賞賛できる制度です。
所定の書式に「物の置き場が決まっていないので、置き場を決めました」や「危険と思われる場所に安全のために柵を設けました」などの改善内容と、改善前・改善後の写真を記載するなどして提出します。いいね賞は、1件提出につき一律の報酬が支払われ、月間賞に選ばれるとプラスで報酬が支払われます。
本社を通さなくても各拠点でやりたいことを実行に移せるという点や、比較的取り組みやすいという点で現場にスピード感が生まれ、社員にも「自分で職場を良くしていこう!」という自覚が生まれ、自発的に行動できる空気を醸成する効果があります。
「改善提案制度」
「改善提案制度」は、改善したいことに対しての費用対効果を提案するという制度です。
改善提案には各部署の承認が必要となり、内容も「いいね賞」より高度なものとなります。
内容が難しいので提案しづらいという点もありますが、モノづくりの会社で表現するのが苦手という社員も多い中、この制度を通じて効果的な表現方法を身につけることができ、周囲により伝わる説明ができるようになる、お客様との交渉にも説得力が増す、というような効果も出ています。
品質向上のための活動「QCサークル」

品質向上のための活動「QCサークル」

数名のグループを作り、困りごとをテーマに1年間を通して活動しています。係長以下の社員はいずれかのQCサークルに所属し、役職者はアドバイザーの立場になります。
QC発表会は年に1回おこなわれ、課長以上の役職者は全員が講評者として参加しています。
表彰制度も設けられ、それぞれに応じた賞金も支払われます。賞の種類は、金賞・銀賞・銅賞のほかにチャレンジ賞・チームワーク賞などさまざまです。
QCサークル活動を機に、従業員の問題解決力が上がるとともに、コミュニケーションを取ることによるチームワーク向上など、組織の活性化にも繋がると考えています。